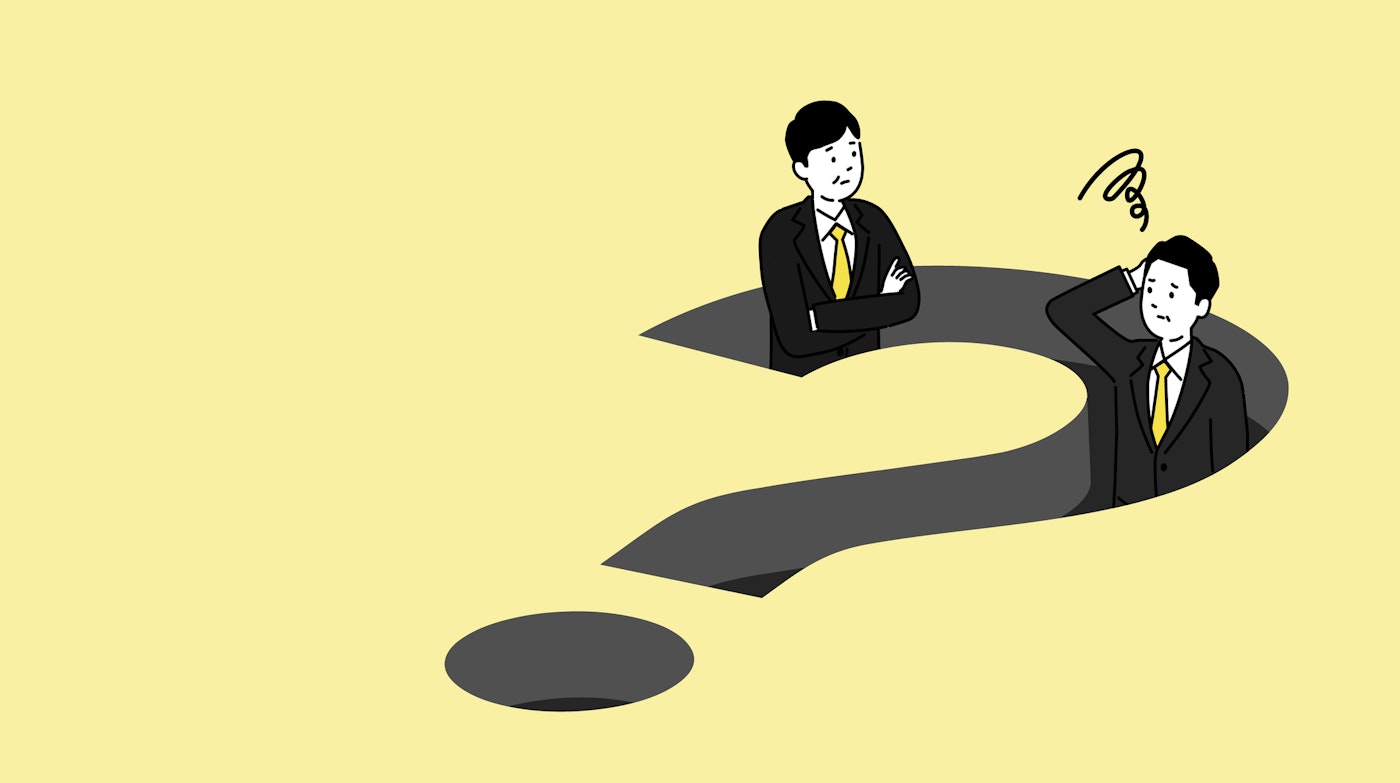なぜ「カーボンニュートラル」が注目されているのか
2020年10月、日本政府が「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と宣言して以来、産業や経済の在り方そのものが脱炭素を軸に動き始めました。その目標は単なる環境施策ではなく、経済競争力を再構築するための国家的プロジェクトとして位置づけられています。
世界ではいま、気候変動に対する危機感がこれまでになく高まっています。国連の専門機関である「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」の報告によると、産業革命以降、人間の活動によって排出されたCO2などの温室効果ガスにより、地球の平均気温はすでに1.5℃を超えつつあります。このまま気温上昇が進めば、大雨や干ばつなどの異常気象が増え、食料や水資源の確保が難しくなると警告されているのです。
各国では「2050年実質ゼロ」に向けた政策や制度整備が進み、企業や金融市場もその流れを受けて脱炭素への取り組みを加速させています。
日本でも「グリーン成長戦略」や「GX推進法(正式名称:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)」のもと、再生可能エネルギー(以下、再エネ)や水素、蓄電池、カーボンリサイクルなど14分野が重点支援対象に指定され、技術革新や新たな産業の創出を後押しする仕組みが整いつつあります。
さらに、ESG投資やサステナビリティ情報開示といった国際基準も整備が進んでおり、企業の環境対応はもはや社会的責任ではなく、資金調達や投資判断、ブランド評価を左右する経営課題となっています。
つまり、カーボンニュートラルは、環境への配慮という枠を超え、企業競争力を支える新たな経営戦略の軸として注目されているのです。
ここで、改めてカーボンニュートラルとは何かおさらいしておきましょう。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いて実質的にゼロにすることを指します。つまり、CO2をまったく出さないという意味ではなく、排出した分を削減や吸収、代替エネルギーの活用などで相殺するという考え方です。
仕組みとしては一見シンプルであるものの、実際に企業が取り組むとなると多くの課題が浮かび上がります。
具体的には、「削減できる部分」と「どうしても残る部分」を分けて管理する必要があり、さらにサプライチェーン全体(Scope1〜3)を含めた排出量を正確に把握・算定する必要があります。

理想とのズレが起きる3つの理由
カーボンニュートラルの仕組みを導入する際、理想と現実の間でズレが生じるケースは少なくありません。
主な理由は次の3つです。
- 対象範囲が広すぎる
- コスト構造が変わる
- 制度・評価基準が常にアップデートされている
それぞれについて詳しくみていきましょう。
1. 対象範囲が広すぎる
カーボンニュートラルの取り組みでは、対象範囲が非常に広い点が大きな課題となります。
製造現場の排出量だけでなく、原料の調達から物流、製品の使用、廃棄に至るまで、ライフサイクル全体を通じて排出量を管理しなければなりません。このため、企業単体で完結できる取り組みは限られ、サプライヤーや取引先などとの連携が必要です。
特にScope3(間接排出)の領域は、取引先や顧客など他社のデータに依存するため、正確なCO2排出量を把握しづらいのが現状です。業界によっては排出係数やデータ共有の基準が整っておらず、算定方法にばらつきが生じる恐れもあります。そのため、自社の責任範囲とデータ管理の手法を明確にし、透明性のある算定体制を築くことが重要です。
2. 企業のコスト構造が変わる
カーボンニュートラルへの取り組みは、企業のコスト構造そのものを変えなければなりません。再エネの導入や省エネ設備への投資、排出量算定ツールの導入など、初期段階では多くの費用が発生します。
特に中小企業においては、短期的な収益を圧迫する要因となりやすく、「環境投資」と「経営の安定化」をどう両立させるかが大きな課題です。また、エネルギー価格やカーボンプライシングの導入によって、ランニングコストが変動するリスクもあります。
こうした変化に対応するためには、単にコスト削減を目的とするのではなく、長期的な経営戦略の一環として環境投資を位置づける視点が必要です。
3. 制度・評価基準が常にアップデートされている
カーボンニュートラルをめぐる制度や評価基準は、常に変化し続けています。SBTi・TCFD・ISSB・EUタクソノミーといった国際的なルールや枠組みは頻繁に更新され、企業はそれらの内容に合わせて自社方針や算定方法を見直さなければなりません。
特にグローバル市場で事業を展開する企業ほど、海外規制との整合性を保ちながら対応する柔軟性が求められます。 こうした変化に遅れると、取引機会の損失や投資家からの評価低下につながるおそれもあるため、継続的な情報収集と体制整備が不可欠といえるでしょう。

カーボンニュートラルの落とし穴
カーボンニュートラルに向けた取り組みが加速する一方で、企業の現場では「理想」と「現実」の間に深い溝が生じているケースも少なくありません。
ここでは、実際の現場で多くの企業が直面する3つの落とし穴と、それらを回避するための対策を詳しくみていきましょう。
1. 再生可能エネルギーを導入すればOKという誤解
再エネの導入は、脱炭素化への第一歩として、多くの企業が取り組んでいます。
しかし「太陽光パネルを設置した」「再エネ電力に切り替えた」だけで目標を達成できるわけではありません。
最大の課題は、「天候に左右される発電量の不安定さ」です。曇りや無風の日には出力が落ちるため、安定供給には蓄電池や制御システムの整備が欠かせませんが、コストや技術面には依然として課題があります。
また、製鉄や化学などの化石燃料を用いる非電力分野では再エネの効果が限定的で、CO2の回収・再利用や水素製造技術の導入が求められます。さらに、原料調達から廃棄までのサプライチェーン全体(Scope3)における排出量の削減や設備導入時の地域合意や環境への配慮も必要です。
このように、再エネ導入は、「ゴール」ではなく「出発点」。省エネや資源循環、技術革新を組み合わせた総合的な取り組みこそが成功に向けたポイントとなるでしょう。
2:カーボンクレジットで帳尻を合わせればよいという誤解
カーボンクレジットとは、他者が削減・吸収したCO2量を取引できる環境価値のことです。
森林整備や再エネ発電などによって削減されたCO2を「1トン=1クレジット」として売買し、自社の排出量と相殺できます。日本では環境省の「J-クレジット制度」が代表的で、企業の脱炭素経営を支援しています。
一方で、「自社で減らせない分を買えば問題ない」と過信すると、本質を見失ってしまうでしょう。国際市場では品質基準が統一されておらず、信頼性の低いクレジットも存在します。さらに、購入だけで「帳簿上ではゼロ排出」と見せかけても、実際の生産体制や供給網が温室効果ガスを出し続けている場合、「見かけ倒しの脱炭素」に陥るリスクもあります。
カーボンクレジットはあくまで補完的な手段です。そのため、まずは自社の排出削減努力を進めたうえで活用することが、信頼ある脱炭素経営につながります。
3:根拠や実行計画が伴わない数字合わせをしてしまう
「2050年カーボンニュートラル」「2030年に排出半減」など、企業のゼロ宣言が相次いでいます。こうした目標は社会的信頼を得やすい一方で、根拠や実行計画が伴わない「数字合わせ」に陥る危険があります。
削減範囲(Scope1〜3)を明示せず「全体で〇%減」とするケースでは、評価機関や投資家からの信頼を失う恐れがあります。また、短期的に見栄えを整えるためにクレジット購入や一時的な事業縮小で帳尻を合わせると、構造改革が進まず、結果的に競争力を損ねることにもつながります。
実効性のある目標には、科学的根拠に基づく定量算定、Scope別の明確化、第三者検証、段階的な中長期計画が欠かせません。たとえば、トヨタ自動車の「2050年までに新車ライフサイクルCO2を90%削減」というように、裏づけと実行計画を伴う目標こそが真の評価につながるでしょう。

現場が抱えるカーボンニュートラルの壁
カーボンニュートラルの実現には、経営層の決断だけでなく、現場の実行力が不可欠です。
しかし、多くの企業では「データが揃わない」「人材が足りない」「社内に温度差がある」といった問題が浮き彫りになっています。
ここでは、脱炭素経営の推進現場で見られる主な3つの課題を詳しくみていきましょう。
1. データ収集と可視化の難しさ(Scope3問題)
企業の温室効果ガス排出量のなかで、最も大きな割合を占めるのが「Scope3(サプライチェーン全体での間接排出)」です。 サプライチェーン全体で発生するCO2排出量を正確に把握し、削減の優先順位を決めるために、素材メーカーや物流、販売、廃棄など、多様な取引先の活動データを収集しなければなりません。しかし、現場では「取引先がデータを出してくれない」「フォーマットが統一されていない」「測定方法がバラバラ」といった課題が多くみられます。
こうした状況を受け、環境省と経済産業省は2023年度から「Green Value Chain促進ネットワーク」を推進しています。この取り組みでは、企業が取引先と連携して排出量を可視化し、削減計画を立てやすくするためのツール導入や人材育成を支援しています。
ただし、可視化はゴールではなくスタートです。集めたデータをもとに、排出削減の優先順位を明確化し、サプライヤーと協働して実効性のある対策に落とし込むことが求められます。
2. 中小企業への波及と支援不足
大企業が脱炭素経営を進めるなかで、その影響は取引先である中小企業にも広がっています。最近では、調達条件として「CO2排出量の開示」や「削減計画の提出」を求めるケースが増えており、対応できない企業は取引が継続できないケースもみられます。
しかし現場では、「人手が足りない」「専門知識がない」「何から始めればよいかわからない」といった声が多く、実務面での支援不足が大きな課題です。
こうした状況を受けて中小企業庁は、中小企業に対する支援機関等のGX支援体制強化事業を強化しています。排出量を簡易的に算出できるツールの提供や、省エネ設備導入への補助金制度など、初期段階から取り組みやすい仕組みを整備しています。
中小企業が最初の一歩を踏み出すには、以下のような身近な改善から始めることが効果的です。
- 電力使用量の「見える化」
- 照明・空調の高効率化による省エネ投資
- 再生紙・バイオ素材など脱炭素型原材料への切り替え
重要なのは、完璧を目指すよりも「できることから着実に進める」姿勢です。小さな一歩の積み重ねが、サプライチェーン全体の脱炭素につながります。
3. 組織文化と人材育成
多くの企業では、脱炭素の取り組みが環境部門だけに任されているのが現状です。しかし、部署任せの状態では、経営全体に浸透せず、継続的な成果を上げることは難しくなります。脱炭素はもはやCSRの延長ではなく、経営戦略の中核として位置づけるべきテーマです。
そのため、経営企画や財務、製造、広報などの各部門が連携し、全社的に意思決定と実行を進める体制づくりが欠かせません。さらに、社内だけで知見を蓄積するのは難しいため、外部専門家や教育機関との連携を図る動きも検討する必要があります。
近年では、大学や自治体、スタートアップなどが提供する脱炭素経営に必要な知識を体系的に学ぶ企業も増加傾向にあり、人材育成と社内浸透の両面で効果がみられています。こうした学びや協働を通じて、組織全体で脱炭素を「自分ごと」として捉える文化を育てることが重要です。
信頼を失うリスク〜グリーンウォッシュとは〜
近年、企業が環境配慮をアピールする機会が増えている一方で、実態が十分に伴っていないケースも少なくありません。このように、実態以上に環境に優しい印象を与える表現や活動を「グリーンウォッシュ(Greenwashing)」といいます。
この言葉は「whitewash(ごまかし)」と「green(環境)」を組み合わせた造語で、1980年代に欧米で生まれました。
たとえば、再生素材の使用率がわずかでも「エコ商品」とアピールしたり、クレジット購入だけで「CO2ゼロ」と表示したりなど、実際の削減と乖離した訴求が該当します。
欧州では2024年に「グリーンウォッシング禁止法」が採択され、科学的根拠のない環境表現に罰則を科す仕組みが整備されました。日本でも消費者庁が「環境表示ガイドライン」を発表し、企業に対して環境主張の根拠明示を求めています。誤った訴求は、投資家・消費者の信頼を損ない、企業ブランドを一瞬で失墜させるリスクがあるため十分に注意が必要です。
グリーンウォッシュを回避するための3つのルール
グリーンウォッシュは、企業の信頼を損なう大きなリスクをはらんでいます。
実態と異なる環境配慮を発信すれば、投資家や消費者の信用を失うだけでなく、政策・法規制の対象となる恐れもあります。
さらに、社内で「形だけの取り組みでよい」という風潮が生まれれば、組織全体のモラル低下にもつながりかねません。
こうしたリスクを防ぐためには、以下の3つのルールを意識することが大切です。
ルール | 内容 |
根拠を示す | データや第三者評価を明示し、主観的な表現を避ける |
範囲を明確にする | 「製品の一部」なのか「企業全体」なのかを明示する |
プロセスを共有する | 結果だけでなく、削減までの取り組み過程を公開する |
たとえば花王株式会社では、自社製品のCO2排出量をLCA(ライフサイクルアセスメント)で算定し、製品にかかわるすべての段階がエコにつながるような取り組みを公開しています。このように、客観的な手法やデータをもとに透明性の高い情報を発信することが、企業への信頼を高めるポイントとなります。
環境への取り組みは「見せ方」ではなく「中身」で評価される時代です。一つひとつの表現やデータの裏づけを丁寧に積み上げることで、グリーンウォッシュを避け、真に持続可能な企業姿勢を示せるでしょう。
企業が学ぶべき「脱炭素経営の事例」
脱炭素経営は、理想だけでは成り立ちません。思い描いたビジョンと現実のギャップに直面する企業もあれば、着実なデータ管理や体制づくりで成果を上げる企業もあります。ここでは、企業が学ぶべき脱炭素経営の良い事例と悪い事例をそれぞれ紹介しましょう。
1. 海外事例:石油メジャーの「再エネ依存型戦略」
英BP(ブリティッシュ・ペトロリアム)は2000年代初頭、「Beyond Petroleum(石油を超えて)」というスローガンを掲げ、積極的な再エネ投資を打ち出しました。しかし、当時も事業の約9割は依然として化石燃料に依存しており、実態との乖離が批判を招きました。
その後、再エネ部門の縮小を余儀なくされ、現在は「エネルギートランジション(段階的な移行)」へと戦略を修正しています。
理想を急ぎすぎる「再エネ偏重型」の戦略が持続性を欠くことを示す事例の一つです。脱炭素経営には、段階的かつ現実的な移行シナリオを描く必要があります。
2. 国内事例:中小企業でも実現した再エネ100%経営
環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」に掲載されている株式会社大川印刷(神奈川県)の事例は、中小企業による実践的な脱炭素経営の好例です。
同社は2016年度にScope1・2(自社排出+購入電力)でCO2排出ゼロを達成し、2030年までにScope3も含めた実質ゼロを目指しています。工場屋根に太陽光発電を設置し、再エネ電力を100%使用。結果、売上8%増・エネルギーコスト8%削減を実現しました。(削減できない部分については非化石証書やクレジット等を用いて打ち消し。)さらに、従業員の意識変革や顧客からの信頼向上にもつながり、「全員がSDGs担当」という文化を育んでいます。
3. 国内事例:日立製作所の「トータル・カーボンマネジメント」
日立製作所は、環境対策をCSRの一環ではなく「経営戦略」として位置づけ、サプライチェーン全体を巻き込んだトータル・カーボンマネジメントを推進しています。
自社の工場・オフィスのみならず、取引先と連携してCO2排出を可視化し、データに基づく削減を実施し、結果として、Scope1+2排出量を2010年度比で64%削減する成果を上げました。
また、「環境ビジョン2050」として2050年カーボンニュートラルの具体的ロードマップを公表し、透明性の高い情報開示を続けています。

まとめ:理想ではなく、現実から始める脱炭素
カーボンニュートラルは理想ではなく、あくまでも「継続するプロセス」に過ぎません。再エネやクレジット、データ可視化、サプライチェーン連携などはもちろん大切ですが、単独では完結しません。何より重要なのは、それらをどのように組み合わせ、現実的に続けていくかどうかです。
カーボンニュートラルは環境だけでなく、経営の持続力を高める取り組みです。他社と比較して焦るのではなく、自社の実情に合わせた第一歩を着実に設計・実行することが求められます。まずは現状を把握し、できる範囲から始めていきましょう。